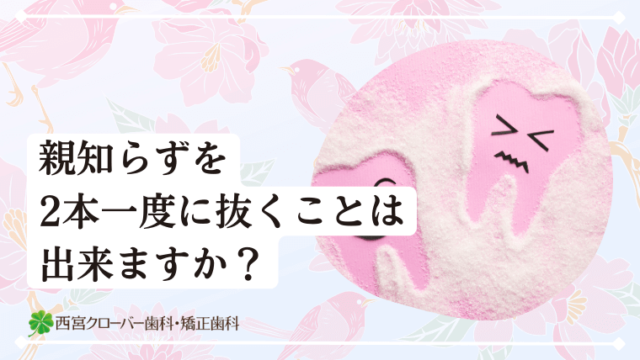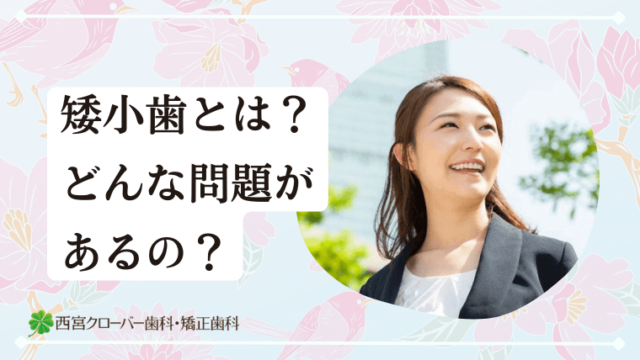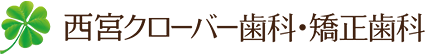デンタルフロスを奥歯にできない…どうすればよい?
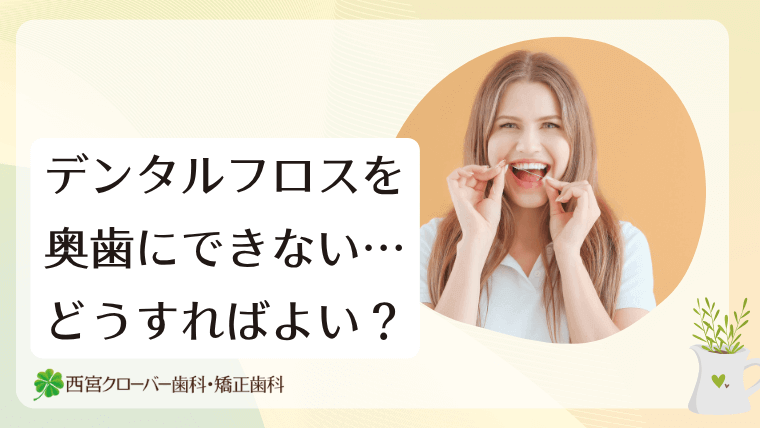
デンタルフロスを奥歯にできないという悩みは意外とよく聞きます。デンタルフロスを使う目的は、歯ブラシのみでは取り除けない歯と歯の間の汚れを落とすことであり、歯間にたまった汚れをそのままにすると、口臭の原因になります。当たり前ですが、前歯よりも奥に位置しているため、奥歯は口が開けにくく、手を動かしづらくできないという影響を受けやすいです。デンタルフロスを奥歯に出来ない原因や使いやすいフロスなど、詳しくご紹介します。
目次
なぜ奥歯にフロスできないかという原因
まず、デンタルフロスを奥歯に通せないという悩みは、経験している方も多いでしょう。前歯は比較的自由度が高く、操作しやすいためフロスを入れやすいですが、奥歯になるほど手指の可動域や口の開き具合、視界の見えにくさ、歯の形などが強く影響します。技術不足や慣れの問題だけではなく、構造的な、あるいは個別の歯の状態の問題が関わっていることが多いです。
フロスが通らないとどうなる?
奥歯にフロスが通らないと、その部位の歯間や歯と歯茎の境目にプラーク(歯垢)が残りやすくなり、歯周病やむし歯のリスクを高めてしまう可能性があります。だからこそ、奥歯にフロスできない原因を知り、対策をとることが重要です。
手、口、歯科医の制限など
では、奥歯でフロス操作が困難になる主な物理的な問題を挙げていきましょう。
指や手の運動範囲が足りない
手の大きさ、関節可動性、指の長さ、手首の柔軟性などが影響します。特に、ロールタイプのフロスを使う場合、左右両手を使って糸を操作する必要があり、奥歯に届かないことがあります。
口を十分に開けられない
顎関節の制限、筋肉のこわばり、顎の痛み、顎関節症、開口障害などで口が大きく開けられないと、口腔後方の奥歯付近にフロスをしづらくなります。
視界の制限
奥歯は見えにくく手元が把握しにくいため、鏡で見ながら行っていても、フロスをどう動かすか感覚がつかみにくくなります。
口腔内の狭さや歯列の並び
歯列が狭かったり、奥歯に傾きがあったり、生え方がやや複雑、隣接歯との距離が近いなどの状態であればフロスを差し込みにくくなります。これらの物理的な問題が重なると、どうしても奥歯でのフロス作業が難しくなることが多いです。
フロスの種類と性質が影響するケース
フロスにはさまざまなタイプがあり、その選び方で奥歯にできるかどうかが大きく左右されます。適切な種類を使ったり、使い分けを行えば、難しさを軽減できます。
ロールタイプ
糸タイプのフロスで、卵型のようなケースに入っており、糸を切り、左右の指で操作します。使いこなせれば隅々まで届きやすいというメリットがありますが、初心者には扱いが難しく、特に奥歯では指の操作が制限されがちです。
ワックス付き/ノンワックス
ワックス付きは滑りがよくて挿入しやすく切れにくいため、狭い歯と歯の隙間や奥歯、被せ物(クラウン)や詰め物(インレー)が多い方には比較的使いやすいでしょう。ノンワックスは滑りはやや悪いものの、糸の繊維が広がるため、表面の汚れをかき出す力に優れる場合があります。ただし、操作性の点ではノンワックスの難易度が上がります。
ホルダータイプ
柄と呼ばれる持ち手のついたフロスで、Y字型とF字型のフロスがあります。手を奥まで入れなくても糸を操作できるため、手の操作が難しい高齢者や子供でも操作しやすいのがメリットです。特にY字型タイプは、横向きに糸が張られている設計で、奥歯にアクセスしやすいよう工夫されています。F字型タイプは前歯向けですが、用途に合わせて併用する選択肢もあります。
香り付きフロスも有り
子供向けにフルーツの香りがついたフロスもあり、歯磨きの際にフロスを習慣化しやすくなります。また、フロスのタイプを変えるだけで、奥歯への通しやすさ、糸の引っかかりにくさ、汚れ除去力などのバランスを改善できるケースが多いです。
歯の状態や補綴物が妨げになることも
単なる操作のしにくさという問題だけではなく、歯そのものや周囲の状態によっても奥歯にフロスできない要因になり得ます。
かぶせ物や詰め物との段差や不適合
古くなったクラウンやインレーなどの補綴物(ほてつぶつ)で、歯との境界に段差や隙間ができていると糸が引っかかりやすくなり、フロス挿入を妨げることがあります。また、浮いていたり、軽く緩んでいるケースでは、糸を通すたびに補綴物と歯肉を刺激してしまうことがあります。
虫歯や歯周ポケット
歯と歯茎の境目付近に炎症や溝があると、フロスを通す際に痛みや出血を感じやすくなり、怖くてやらない原因になります。また、虫歯が進行していると、歯の形状が変化していることから、隣接面が複雑になることがあります。
歯の傾きやねじれ、接触点が強い
隣り合う歯との接触点(コンタクトポイント)がぎゅっと強い場合、糸を通すのが物理的に難しくなります。歯が斜めに傾いていたり、歯列のアーチが湾曲していたりすると、糸のルートを取りにくいです。
これらの歯、補綴、形状については、単純に操作を工夫するだけで解決できないこともあるため、注意が必要です。
奥歯のフロスの選び方のポイントと使いやすいタイプ
奥歯にフロスを通すためには、適切なフロスの選び方と使いやすいタイプを知ることが重要です。
選び方のチェックポイント
- フロスの長さや糸のたわみ具合
- 持ち手のデザイン
- 糸の太さ、強度、滑り具合(ワックス/ノンワックス)
- 糸の抵抗や毛羽立ちの少なさ
奥歯に使いやすいタイプ
選び方のポイントを踏まえたうえで、使いやすいタイプを知りましょう。
Y字型ホルダータイプ
持ち手を口の外側に固定したまま、糸部分だけを奥まで届かせやすいため、手の届きにくい奥歯向けの定番です。
ワックス付きタイプ
滑りがよいため、きつめの接触点や狭いすき間にも通しやすく、奥歯操作では扱いやすさが優れる傾向があります。
柔軟性や弾性のある糸
硬すぎる糸だと角度をつけにくくなるため、ある程度しなやかさのあるものを選ぶと、歯面に沿って引き込みやすくなります。
フロスの種類を複数持っておき使い分けるのも良いでしょう。例えば、前歯はF字型フロス、奥歯はY字型フロスを使用するというアプローチも効果的です。
奥歯にフロスを通すためのテクニック
奥歯に使用しやすいタイプを使っても、使い方を習得できていないと、通そうとした時に難しく感じることがあります。フロスを通すためのテクニックについてご案内します。
角度をつけて差し込む
糸を真上から垂直に差し込もうとするよりも、やや角度をつけて斜めから滑らせながら入れると通りやすくなります。
のこぎり引き動作で少しずつ進める
糸を少しずつ前後に動かしながら、のこぎりのような動作でゆっくりと進ませるように操作すると、無理なく隙間に入ります。
歯面に沿わせるくの字形アプローチ
糸をくの字またはC字にして歯面に密着させ、歯と歯茎の境目に沿って上下運動を加えつつ動かすと汚れを落としやすくなります。
片側ずつ慎重に操作する
左右を無理に同時に扱おうとすると糸がたるんだり、余裕がなくなります。片側ずつ安定させて操作することでコントロールしやすくなります。
鏡を使って目視しながら行う
鏡を使って糸の動きや角度を確認しながら操作すると、最適なルートを見つけやすくなります。
新しい糸やワックス付きの糸を使う
摩耗したり毛羽立ちをした糸は通りが悪くなるため、常に新しい糸を使うのが望ましいです。特に奥歯では摩擦が強く起こるため、ワックス付き糸を試すと通りやすくなります。
無理せず少しずつ進める
歯間や歯周ポケットに強引に通そうとすると、糸が切れたり歯茎を傷つけたりする恐れがあります。痛みや抵抗を感じたら方向を変えてみたり、角度を変えるなどして再挑戦しましょう。
無理に通すと危険なケース
奥歯にフロスを強引に通してしまうと、口腔内にトラブルが起こる可能性があります。
| リスク項目 | 内容および影響 |
|---|---|
| 歯周組織の炎症や出血 | 歯茎に無理やり押し込むと、歯茎を切って出血したり炎症を悪化させる可能性あり。 |
| フロス糸の断裂や断片残留 | 補綴物の段差や引っかかりで糸が切れ、断片が歯間に残ることがある。取り出せない場合は歯科医院で除去が必要。 |
| 補綴物の損傷 | クラウンや詰め物の接着部や縁部を傷つけたり、補綴物が緩む原因になる。特に古い補綴物は注意。 |
| 痛みや知覚過敏の悪化 | 敏感な歯面に強く接触させることで、知覚過敏や痛みを誘発する可能性がある。 |
それでも難しければ歯科医院で相談を
万が一、どのようなフロスタイプや工夫をしても奥歯にフロスを通せない、または糸が引っかかったり、痛みが出る、断裂するなど不具合が残る場合は、自己判断を続けるよりも歯科医院での診察を強くおすすめします。難しいと思えばその歯にはフロスではなく別のタイプや方法を試すか、歯科医師や歯科衛生士に相談することが安全です。
- 補綴物の適合チェック
- 隣接歯との接触関係や傾きのチェック
- 歯周ポケット、炎症、歯茎の状態の確認
- 隠れた虫歯がないかの確認
- 歯のねじれや動揺などはないかの確認
- 専用器具や、フロス、歯間ブラシ併用などでお口の清掃状態をサポート
歯科医院ではこのようなことが確認出来ますし、歯科衛生士からはあなたの歯列や口腔状態に適したフロスの使い方や角度や選択を提案してもらえるはずです。
まとめ

デンタルフロスで奥歯ができないと悩んでおられたら、他のフロスの種類を試してみましょう。フロスを奥歯に通せるようになることが目的ではなく、すべての歯間や歯周部を清潔に保つことが目的です。フロスが難しい場合は、代替となる歯間ブラシやウォーターフロスなどを組み合わせて補うという考え方もあります。どうしても奥歯の口臭で悩んだり、フロスを通すことが難しければ、歯の専門家である歯科医院へ相談してください。
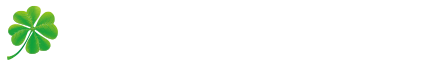
 医療法人真摯会
医療法人真摯会