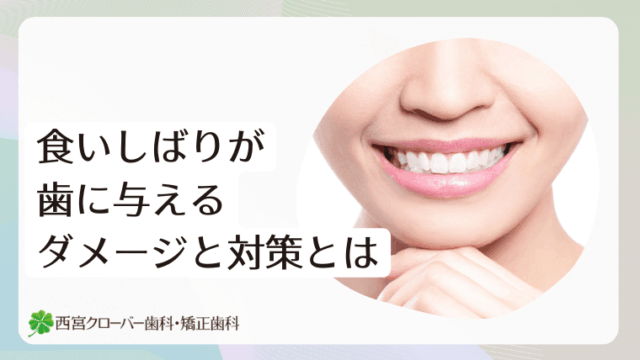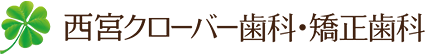歯茎に水ぶくれ?どうすればよい?
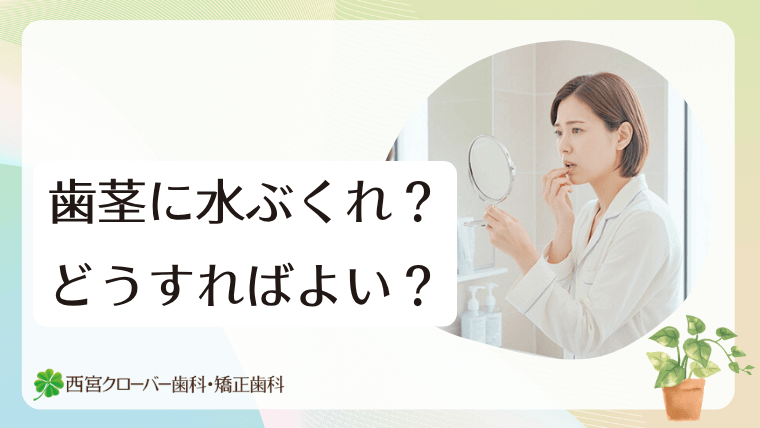
歯茎に水ぶくれができていれば、ニキビのようにつぶして良いのかな?と思われるでしょう。水ぶくれができる原因は何か、どのような処置をすればいいか、見分け方も含めて詳しくご紹介いたします。
歯茎に水ぶくれ?
歯茎に水ぶくれは、あまり耳慣れない症状かもしれません。どのような状態が水膨れと呼ばれているのかを整理しましょう。歯茎の粘膜上やそのすぐ下に、透明もしくは白っぽい液体や膿が溜まり、丸く膨らんだように見えるものを水ぶくれ、嚢胞(のうほう)状の膨らみと呼ぶことがあります。
- 歯肉の一部に突然ポコッとした膨らみが出来る
- 色が透明~淡い白、あるいは少し黄色味を帯びていることもある
- 水が溜まっているように見える
- 痛みがほとんどないものから、強い痛みを伴うものまで幅がある
このような歯茎の水ぶくれは、軽い刺激のみで起きるケースから、口腔内で進行している別の感染や炎症などのサインであるケースもあります。そのため、歯茎が膨らんでいると感じたら軽視せず、どのような原因で起きたのかを知っておくことが重要です。
水ぶくれができる原因
歯茎に水ぶくれができる原因は多岐にわたります。
日常的な刺激や外傷
- 硬い食べ物を噛んだり、歯茎に強く当たったとき
- 歯ブラシで強く磨きすぎたり、歯間ブラシやフロスを無理に使い歯肉を傷つけたとき
- 口腔内での打撲や、熱い飲食によるやけど
物理的な刺激が、歯茎の浅い粘膜下に液体を溜めてしまい、水ぶくれのような膨らみを生じさせることがあります。
アレルギー反応や薬剤の影響
特定の食品や薬剤に対してアレルギー反応が出て、歯茎の粘膜がむくんだり、腫れを起こします。薬による歯肉の腫れのメカニズムは、一部の薬剤が歯肉の線維芽細胞に作用し、コラーゲンなどの結合組織成分を過剰に作らせることで、歯ぐきの結合組織が増え、厚く盛り上がるように腫れます。同時に、薬の影響で歯肉の代謝や血流が低下し、細胞の入れ替わりが遅くなることで腫れが持続し、歯垢が溜まると、炎症性の腫れがさらに加わることもあります。つまり、薬の直接的な作用と口腔内の清掃不良による炎症の両方が関係しています。
抗てんかん薬フェニトイン
けいれんを抑えるために使用される抗てんかん薬フェニトインを長期間服用すると、50%以上の方に歯ぐきの腫れが見られると報告されています。フェニトインは歯肉の細胞の増殖を促しやすく、特に口腔内の清掃状態が悪いと腫れが顕著になる傾向があります。
高血圧治療薬カルシウム拮抗薬
血圧を下げるためのカルシウム拮抗薬を長期間服用している方では、約20%程度に歯ぐきの腫れが発生すると言われています。薬剤による血流変化や細胞代謝の影響で、歯肉の線維成分が増加しやすくなるためです。
免疫抑制剤シクロスポリン
臓器移植後の拒絶反応を防ぎ、自己免疫疾患の治療に用いられるシクロスポリンも、歯ぐきの腫れを引き起こす代表的な薬です。細胞の成長を制御する働きが変化し、歯肉組織が厚く盛り上がるように増殖することがあります。この症状は歯垢の付着量と関係性があり、口腔清掃を徹底することが重要です。
口内炎や粘膜炎などの炎症
免疫力の低下、栄養不足、ストレス、細菌、ウイルスの感染などが原因で口内炎が発生し、その範囲が歯茎にまで及ぶと、水ぶくれ状の出現につながることもあります。
感染症
細菌やヘルペスウイルスの感染により、歯根の感染が原因となり、膿が歯茎から排出されるフィステル(瘻孔)ができ、その結果として水ぶくれのように見える膨らみとなるケースがあります。
粘液嚢胞
小さな唾液腺から伸びる唾液の通り道が、何らかの原因で傷つき詰まると、作られた唾液が正常に口の中へ流れ出ず、粘膜の下に溜まってしまいます。唾液が粘膜の下にたまって袋状になる状態を粘液嚢胞と呼びます。唇や頬の内側にできることが多いですが、稀に歯肉でも導管の詰まりなどによって唾液が溜まり、透明から青みがかった小さな水ぶくれとして現れることがあります。
原因は軽度の刺激から重大な感染症まで幅があるため、単に水ぶくれだからと放置しないようにしましょう。
水ぶくれの代表的なタイプと見分け方
歯茎に水ぶくれが現れたとき、その中身によって分類できます。見分け方を知ることで、歯科を受診すべきかどうかの判断材料にもなります。
| タイプ | 特徴 | 痛み・症状 | 備考 |
|---|---|---|---|
| フィステル | 歯茎の表面に白〜黄色の膿が溜まった小さな膨らみ。特定の歯根の奥に原因があることも。 | 強い痛みはない。膿が出るとスッと引くことも。 | 原因を放置すると骨を溶かすリスクも高い。 |
| 歯肉ヘルペス | 歯茎や口腔内、唇に多数の小さな透明〜白っぽい水ぶくれ。ウイルス感染が原因。 | 強い痛みや発熱、口腔全体の不快感を伴う。 | 再発の可能性があり、免疫力低下時に出やすい。 |
| 粘液嚢胞 | 透明または青みがかった水ぶくれ。唾液腺の導管が傷つき、唾液が溜まり、歯茎にできる。 | 痛みはないが、潰れると唾液が出ることも。 | 長引けば摘出が必要な場合もある。 |
| 刺激や外傷性水ぶくれ | 硬い食べ物で歯茎を圧迫、歯ブラシが強く当たるなど。軽度の液体貯留。 | 軽い違和感で痛みは少なめ。 | 日にち薬だが、頻繁なら注意 |
見分けるポイント
色や痛み、いつできたか、特定の歯の部分かと確認することで、ある程度リスクが高いかどうかを把握できます。
痛みの有無
- 痛みがほとんどなければフィステルや粘液嚢胞の可能性
- 反対に強い痛みや発熱を伴うならば歯肉ヘルペスなどウイルス性の可能性
対象の歯
- 特定の歯の近くや根の方向に膨らみがあればフィステルの可能性
- 歯茎の広範囲に多数散在している水ぶくれならば歯肉ヘルペスの可能性
色や中身
- 透明、もしくは淡白な色の液体であれば、外傷性や粘液嚢胞の可能性
- 白~黄色の膿状であればフィステルの可能性
- 水ぶくれが潰れてただれていれば歯肉ヘルペスの可能性
経過や期間
- 通常数日~1週間であれば外傷性
- 2週間以上継続、治った後にぶり返したりする場合は受診
歯茎に水ぶくれが起きたときの症状チェックリスト
実際に歯茎に水ぶくれを見つけたとチェックすべき症状をリスト化しました。
チェックリスト
奥歯か、前歯か、歯と歯の間か、被せ物などどこに膨らみがあるか
色は透明か、淡白か、白っぽいか、黄色味あるか、青みがかっているか
小さな点か、大きな数ミリの膨らみか、触ったときに柔らかいか硬めの形状か
何もしていなくてもズキズキする痛みがあるか
食事や歯磨き時に痛みが増すか
歯茎の赤みや腫れ、出血があるか
口臭や味覚の変化、発熱やリンパの腫れの有無
できてから何日経過しているか
その期間で改善しているか、それとも悪化しているか
硬い食べ物を噛んだり強く歯ブラシを当てたり、口腔内のやけどや打撲をした
被せ物や入れ歯が当たっていたり、歯根の治療中、もしくは虫歯があった
最近疲労や睡眠不足、免疫低下の自覚があるか
治療及び対処法
歯茎に水ぶくれが現れた時、どういった対処をすれば良いのでしょう。原因別に、代表的な治療法を見ていきます。
フィステルへの治療
虫歯の深部や歯根先の感染が原因であるため、膿の出口として歯茎に膨らみが現れます。虫歯の根の内部の感染を取り除き、消毒して薬詰め、密閉をする根管治療を行います。歯の保存が難しい場合は抜歯が選択されることも考えられます。放置すると歯槽骨が溶けたり、慢性的な膿の排出が続き、他の歯への影響も増してしまいます。
ヘルペスへの治療
ヘルペスウイルス感染症による歯茎や口粘膜の水疱が潰瘍化するため、抗ウイルス薬(アシクロビル、バラシクロビルなど)を服用し、ウイルスの増殖を抑制します。同時に痛み止めや、うがい、口腔内清潔保持などもしたうえで、再発予防として、ストレス管理や睡眠、免疫力の維持が重要です。ヘルペスのウイルス自体は完全になくならず、体調を崩した時に再発する可能性があるという点は覚えておきましょう。
粘液嚢胞への対処
唾液腺の導管が傷ついたり詰まることで、唾液が組織内や歯茎に留まります。多くの場合は自然に破裂し消失することもありますが、長く残ったり、大きくなったり、痛みや出血などを伴う場合は歯科口腔外科での摘出や治療が検討されます。
軽度な刺激や外傷性の水ぶくれへのセルフケア
原因は物理的刺激なので、まずは刺激を避けましょう。歯磨き時は強く擦らず柔らかめのブラシを使用し、硬いものや熱い飲食物を避け、歯茎を休ませるのも大事です。うがいやマウスウォッシュで口腔内を清潔に保ち、数日以内に改善しなければ、歯科医院で相談をするのが望ましいです。
予防とセルフケア
歯茎に水ぶくれができてから慌てるより、日頃から予防やケアをすることが理想です。歯茎の健康を維持するためのポイントをまとめます。
正しい歯磨き習慣
ブラッシングは優しい力で小さい円を描くように丁寧に行い、歯茎を傷つけないことを意識しましょう。歯ブラシは硬めではなくふつう、やわらかめの毛質を選び、毛先が開いたら早めに交換してください。歯間ブラシやフロスを使う場合は、歯茎を直接傷つけないよう慎重に優しい力で入れましょう。定期的に歯科で歯石除去や歯茎のチェックなどのクリーニングを受けることも効果的です。
食生活や生活習慣の見直し
ビタミンB群、鉄分、亜鉛は粘膜や歯茎の健康に貢献するため、栄養バランスのとれた食事をしましょう。免疫力低下を防ぐために、睡眠や休息時間をしっかりと確保してください。ストレスが蓄積すると口腔内のトラブルが起きやすくなるため、適切にリラックスする時間を持つのも良いです。
口腔内の環境整備
食後や就寝前にはうがい、洗口液の使用などで細菌の増殖を抑えましょう。被せ物や入れ歯、矯正装置などが当たって歯茎を圧迫していないか定期的にクリニックで点検するのがベストです。喫煙や過度のアルコール摂取などの習慣がある方は、控えることで歯茎の回復力を高めることができます。
日々のセルフチェック
鏡で歯茎の色が淡いピンク色かどうかが確認し、腫れや膨らみ、出血がないかを見てください。歯磨き時に歯茎に痛みや違和感がないかについてもチェックしましょう。硬いものを噛んで歯ブラシでゴシゴシしたなど、原因が思い当たる場合には数日注意して様子を見て、改善しないなら受診を検討するべきです。
こんな時は歯科を受診すべき?
歯茎に水ぶくれができて次のような状況ならば早めに歯科もしくは口腔外科を受診しましょう。原因となる歯や歯茎の状態など、歯科医師の診断を仰ぐ方が賢明です。
受診をおすすめするケース
膨らみが2週間以上続いている
水ぶくれが破れてただれや潰瘍になっている
飲食や歯磨きで強い痛みを感じる
発熱やリンパ腺の腫れがあり、口臭が強くなった
特定の歯で噛むとずきっと痛む、歯がぐらつく
歯茎の中で膿が溜まっているような感覚がある
被せ物や入れ歯、矯正装置で違和感があり、常に圧迫されている
糖尿病、ステロイド治療中、高齢者など免疫力が低下している
受診時に歯科医師に伝えるべきこと
- いつからどこに膨らみを感じたか
- 痛みや出血、違和感はあるのか
- 硬いものを噛んだり、強く歯ブラシを当てたり、被せ物や入れ歯が当たっているか
- 発熱、リンパ腺の腫れ、口臭の変化などがあるか
- 虫歯や根管治療中、入れ歯や矯正治療中などの状況であるか
情報を伝えることで、歯科医師が外傷性、感染性、ウイルス性を早期に判断し、適切な治療や処置を組み立てる材料になります。
まとめ

歯茎の水ぶくれは、軽い刺激や外傷だけで起きるものから、歯根の深い感染やウイルスの影響という重要なサインまで、原因の幅がとても広いです。表面的にはプクッと膨らんでいる、透明~淡白な液体が溜まっているといった見た目でも、痛みや期間、位置、色、原因をしっかりチェックすれば、ただの口内炎か要治療かが見えてきます。また、日頃から歯茎を傷つけない丁寧な歯磨き、栄養、睡眠、ストレス管理、定期的な歯科検診などの予防習慣が、水ぶくれの発生を未然に防ぐうえで非常に有効です。
歯茎に水ぶくれができたけれど様子見していたり、数日たっても治らず痛みが強くなった場合は、早めに歯科を受診し、原因を明らかにして適切な処置を受けることをおすすめします。あなたの口腔内が健やかに保たれるよう、日々のケアと早期対処を心がけてください。
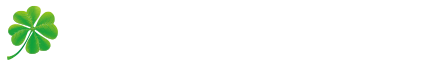
 医療法人真摯会
医療法人真摯会